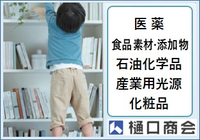Perfect for small-scale testing! Mixer Torque Rheometer 3 (MTR-3)
Optimal for examining the best granulation conditions! Accelerate research and development!
- Speeding up research and development! - Optimization of formulations - Simplification of scale-up considerations - Streamlining batch management
basic information
The Caleva Mixer Torque Rheometer (MTR-3) is widely used as a tool for examining the optimal amount of granulating liquid to add during wet granulation formulation. The MTR-3 measures the shear stress generated within the mixing container as torque when mixing wet powders, making it a useful tool for formulation studies, manufacturing process development, scale-up considerations, and process management.
Price information
Please contact us.
Delivery Time
Model number/Brand name
Caleva Process Solutions Ltd. (UK)
Applications/Examples of results
Prescription review tool
catalog(1)
Download All CatalogsNews about this product(2)
-

We will be exhibiting at the Interfex Week Osaka - 3rd Pharma Lab Expo Osaka.
We are pleased to announce that we will be exhibiting at the 3rd Pharma Lab EXPO Osaka. At the venue, we will showcase a variety of unique products from both domestic and international sources, including new products. We understand that you may be busy during this period, but we sincerely look forward to welcoming many of you, along with your colleagues. 《Main Exhibited Products》 Sterilizing Capsule Filter Asepti Series (Advanced Microdevices) Assembly Tubes and Bags (Advanced Microdevices, WHK BioSystems) 3D Printer for Solid Dosage Form Manufacturing M3DIMAKER (FabRx) Formulation Development Tool Mixer, Torque, Rheometer 3 (Caleva) SEDDS Formulation Starter Kit ABISOL Emulsion Kit (ABITEC) Continuous Liner System, Single-Use Binding Tool (Lugaia), etc.
-

I presented a poster on MTR at the "Pesticide Formulation and Application Methods Symposium."
On October 6 and 7, 2016, at the Kanagawa Prefectural Hall, we introduced MTR* in a poster presentation at the "Pesticide Formulation and Application Method Symposium." (*MTR... Mixer Torque Rheometer) Director Keijiro Terashita of the Osaka Life Science Lab presented the collaborative research conducted by the Osaka Life Science Lab, Dalton Co., Ltd., and our company. The poster exhibition received a tremendous response, and we received many questions during the networking event. Currently, in pesticide manufacturing, the main process is "wet granulation → extrusion → drying and granulating," and since granulation often relies on intuition and experience, some participants expressed interest in the necessity of measuring granulation degree. For more detailed information regarding Director Terashita's presentation on "Investigation of Water Content Based on Stirring Torque Measurement and Granulation Index and Extrusion Granulation," as well as information about MTR, please contact us at the following: <Contact Information> iyaku@higuchi-inc.co.jp TEL 06-6448-5533 Contact Person: Furuno
Recommended products
Distributors
Starting as an import trading company in 1927, we have been developing our business with many overseas suppliers and domestic customers over the years. Through our services of connecting the two together, Higuchi has become the well trusted "Japan distribution channel" for suppliers, and the "dependable vendor" who provides a stable supply of the latest high-valued overseas products to customers. Today, we conduct not only importing but also exporting businesses, trilateral trades, and overseas business investments as well. We have also expanded to local subsidiaries in the United States and China, to which we are able to effectively network overseas. Higuchi believes in the criticalness of providing a stable supply to customers, and we also place the highest priority on the coexistence with suppliers, to whom we can mutually develop together in a long-term perspective. Your support and consideration to our corporate philosophy would be much appreciated.